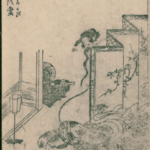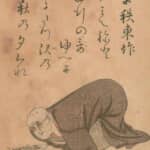渋沢栄一も賞賛した松平定信の「仁政」
蔦重をめぐる人物とキーワード㉙
■天明の大飢饉で餓死者ゼロを達成した定信
江戸の三大改革のひとつである「寛政の改革」を主導した老中首座・松平定信は、厳格な政策で知られる。しかし、老中在任はわずか6年間(1787年~1793年)に過ぎない。その約5倍にあたる29年間は、白河藩(現在の福島県白河市)の藩主として過ごしている。その間、領民を支える数々の「仁政」を実施した事実は意外に知られていない。
定信は、徳川吉宗の孫という高貴な出自ながらも、当時の老中・田沼意次との対立から不本意ながら白河藩主の養子となったという経緯がある。
定信の実績で特筆すべきは、藩主を継いだ1783(天明3)年に深刻化した天明の大飢饉への対応だ。
奥州で多くの餓死者が出る中、定信の白河藩では一人も餓死者を出さなかったという。彼は、飢餓で困窮する領民を救うため、会津藩などからの米の緊急輸送を手配し、さらに「人別扶持(にんべつぶち)」という画期的な制度を導入。これは同年10月から約1年間実施された、身分に関わらず家族総人数に応じて米を支給する制度だ。豪農商からの米や金銭の工面も命じるなど、多角的な対策で領民の窮状を救ったのである。
飢饉の後も定信は藩政に力を尽くした。自ら率先して質素倹約に励み、財政再建を推進。翌1784(天明4)年には領民の不満緩和と役人へのけん制を狙い、目安箱を設置して領民の声に耳を傾けた。
1791(寛政3)年には藩校「立教館」を設立して学問を奨励するなど、文武両道を重んじる姿勢を鮮明にしている。
福祉政策では、人口減少の一因であった間引き(子供を間引く悪習)を防ぐため、出生時に養育料を支給した。1789(寛政元)年には越後領から結婚希望の女性を募り、結婚支度金支給で白河への移住を促すなど、少子化対策も実施している。
また、絹織物や漆器などの諸産業を育成し、貧しい町人にも職を与えられるよう配慮。身分に関わらず誰もが楽しめる南湖公園を造成したことも、領民の生活を第一とした定信の手腕を象徴する事業として広く知られている。
老中解任後も藩政に専念し、藩校の拡充やロシアの脅威に対する軍備充実に努めた。その先見性と「仁の精神」は、明治の実業家・渋沢栄一が高く評価している。
1929(昭和4)年6月14日に東京商工奨励館で行なわれた楽翁公(らくおうこう/定信)百年祭の講演で、渋沢は「ただの政治家でなく、経済的にも社会的にも充分手腕のある方」と定信を褒め称えており、深く傾倒していたことがうかがえる。
現代の白河市でも、定信の業績を伝える特別授業や講談会が開かれ、その精神が次の世代に受け継がれている。
- 1
- 2